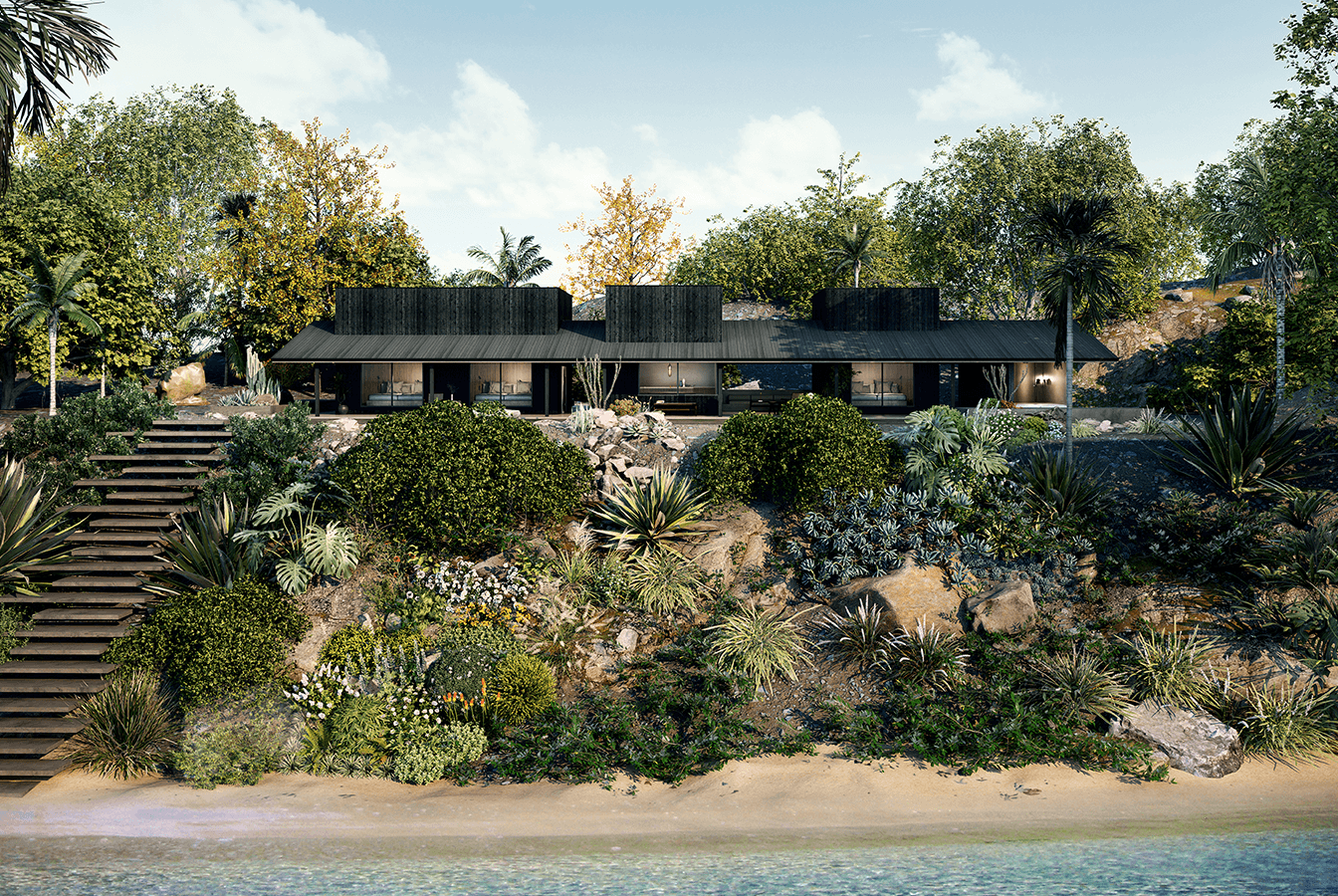Trip
Issue : 34
白藤 | 築150年の邸宅で、重なる3つの層に身をひそめれば
長野県北部に位置する須坂市。明治期に製糸業で栄え、今でも蔵造りの建物が立ち並ぶ小さな街に、築150年の登録有形文化財を貸し切って泊まれる贅沢すぎる宿がある。当時の暮らしそのままの痕跡と今の美意識が入り混じる混沌に、無数の暮らしのヒントが詰まっていた。
もしかして明治期にワープした?広大な私有地の奥行きに唖然

街並みにとつぜん暖簾が揺れている。いかにも武家屋敷というような重厚な門をくぐると、森の玄関みたいな可愛らしい木造の門がまたひとつ。「白藤」と書かれた看板がこちらを向いている。
無数の木々の先には赤い座布団がなかよく並んでいる。奥行はおそらく20mくらいだろうか、舞台セットかと見紛う庭先を横目にまずは、左手の母屋に向かう。

引き戸を開けると12畳の玄関口、8畳のダイニング、10畳の居間が奥までどんと突き抜ける。この家には はじめは須坂藩の要職が、明治後期には医師が住んでいたのだという。箱庭か宇宙にでも迷い込んだみたいな不思議な感覚を紐解いて、明治後期の家づくりから暮らしのヒントを紐解きます。

閉じない仕切りと食べればなくなる果実。
玄関、ダイニング、リビングと3つの空間は繋がれて限りなく開かれながらも、両脇の障子がそこは3つの別々の空間であるのだということを強調している。各部屋の卓上にたっぷりと置かれた果物が目線を誘い、それらも部屋のリズムを生み出している。もちろん果物を食べ切れば自ずと部屋のリズムも変わるわけで、閉じることのない仕切りといいこれらの「弱い境界線」が部屋を心地よく3つに積層させている。

鏡のような3つの奥行き
渡り廊下を過ぎればその先には洋館が。右手を見ると鏡にベッドやその他が映ってて、あれ私いないぞ?と思うと鏡だと思っていたそれは単に扉の開いた空間で、これまた3つの部屋が鏡写しのように奥まで突き抜けているのだということに気づく。医療機器を入れていた棚は食器棚へと活用しながら、当時診療所だった建物の多くがほとんどそのままに活用されている。


動線が習慣をつくる
台所の一番目立つところにお抹茶を点てられる一式が置かれていて、毎朝ここでコーヒーの代わりに抹茶を飲んでみたら気分良く目が覚めた。ちょうどいいところに置かれた団扇を手にとってあおぐと、冷房とは違って風がなんとも柔らかいことに気づいたりする。動線上のモノの存在によってこうも習慣が変わるのか。日々の中で取り入れたいけど習慣化できていないものがあれば、置き場所を工夫すれば生活に染み込んでくるのだなあと気付かされるうれしい配置が幾つもある。


体感的「涼」、視覚的「涼」
「取り外すか本当に迷ったんです」とオーナーが語る涼しげな簾戸(すど)。簾をはめ込んだ夏仕様の建具のことで、「夏障子」などとも称される。かつての日本人は6月頃になると障子や襖を夏に向けて取り替えていたのです。庭先の藤棚は視覚的にも涼しい上に直射日光を防ぎ、ふと飾られた団扇は仮に仰がずとも涼しい。古民家は「夏をいかに過ごすか」の工夫の宝庫。密封されエアコンが効いた部屋にはない、目で涼む喜びがあることに気付かされます。

知恵を絞れば新聞紙も生活のサイクルに
生ゴミは新聞紙で包むと最も匂いが出ないという。ここでは、かつての生活の知恵のうち今もなお便利な習慣を無理なく取り入れた結果、ひとつも無理のないそのまんまの生活が、結果的に暮らしにも地球にも優しくなっているのです。ビニール袋が目に入ると景観を損なうけれど、新聞紙がそっと重なる様子は家にきゅんと馴染むのが不思議です。

居場所は自然と生まれる、廊下にも
庭の奥に並んだ赤い座布団が素敵ですねと伺うと「あそこに座っている人が多かったから、座布団を置いたんです。」と思いがけぬ返答が。住みながら特等席を見つけるのも乙ですね。座布団ひとつ置くだけで、廊下が、窓辺が、すっかり特等席になるのですから。

yado's pick up item #1
古民家の本館には道一さん、洋館には知子さんの作品を中心に器が選ばれた戸棚はどれも魅力的。特定の作家さんを決めて器を集めてみる、そして、空間やシーンで使い分けてみる。器の楽しみ方が広がりそうなヒントです。

yado’s pick up item #2
古民家にも洋館にも、白黒の色を使い分けて設置されていたのがバルミューダ の扇風機。洋室に置けば洋室に、和室に置けばそっと和室に馴染むデザインがちょうどよく、充電式のためコードレスですっきりと配置できるのも魅力です。


Editor’s Voice
-
白藤は高級旅館さながらの豪勢な造りの宿で、なのに感覚的にはおばあちゃんの家に帰省したみたいな心地がするのだけれど、それはオーナーのまりなさんの飾らない人柄や、お母様の郷土料理の不思議な懐かしさによるものなんだと思う。谷崎潤一郎は著書の中で「美というものは常に生活の実際から発達するもの」と説いているが、この家にはまさに染み付いた「生活」の数々を感じずにはいられない。この魅惑的な牧歌的ラグジュアリーの体験は他にはなかなかないのでは。
Rie Kimoto (yado)